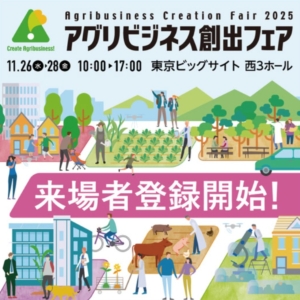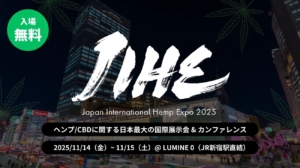期待高まるも依然として課題あり
昨年(2024年)は、恒久的な炭素除去(Permanent Carbon Removal)の分野にとって飛躍的な年となりました。2023年比で78%もの成長を記録し、さらにEUの「炭素除去およびカーボンファーミング規則(CRCF:Carbon Removals and Carbon Farming Regulation)」が発表されたことも追い風となりました。
現在、バイオ炭(Biochar)を用いた炭素固定を手がける高~低技術のサプライヤーが、自主的炭素市場(Voluntary Carbon Market)の主導的存在となっていますが、EUの新たな規制枠組みでは、炭素を長期間固定できる「長寿命製品」への炭素貯留も対象に含まれる見通しです。
例としては、省エネ型の建材などが「カーボン・シンク(炭素吸収源)」として評価されるようになります。
この動きは、産業用ヘンプ業界にとっても朗報といえます。というのも、ヘンプは炭素収支がマイナス(=CO₂を吸収し、排出より多く固定する)であるうえに、CO₂吸収量が非常に高いという特性を持っており、バリューチェーン全体で経済的利益を得られる可能性が広がるからです。
品質こそが競争を制す
100年間の炭素除去が求められる現実
複雑かつ高コストな現実
上記のような厳格な要件をすべて満たしながらプロジェクトを設計し、収益性のある炭素クレジット事業として構築するには、多大な時間・資金・専門的リソースが必要です。
とはいえ、これらの投資は“無駄”ではありません。産業用ヘンプ業界も、炭素クレジット市場も、イメージの失墜を避ける余地はありません
長期的に気候貢献を認められ、関係者が持続的に恩恵を受けていくには、「高品質で信頼性ある炭素除去」を継続していくための強固な評判(レピュテーション)が不可欠です。
ただし現実には、茎以外の部分(葉・花・種など)を主に活用しているヘンプ農家にとっては、炭素を多く含む繊維質の「ストーク(茎)」よりも、むしろ「ハード(芯部)」をバルク(大量)販売した方が収益性が高い場合もあるため、炭素除去向けのプロジェクト化はインセンティブが弱いという構造的な課題もあります。
さらに、高性能なバイオ炭プロジェクトは初期投資が非常に大きく、設備計画も複雑であることから、年間で数千トン単位の処理が可能な大規模事業者でなければ成立しにくいのが実情です。
こうした大規模設備では、原料としては粉末状のダストを使用し、さらに熱分解(パイロリシス)時に発生する余剰熱を回収・利用できるという副次的なメリットも得られる構造になっています。
職人による…バイオ炭
コンティキ窯(Kon-Tiki kiln)や土坑(soil pit)といった、低コストかつ簡易導入型の技術を用いた「職人バイオ炭(Artisan biochar)」の生産は、小規模農家による導入の“入り口”として非常に有望です。
この手法では、バイオ炭を同一の農場内で生産・混合・施用まで一貫して行うことが可能で、局所的な生態系にも良い影響を与えるとされています。農業の本業と並行して副収入を得る手段としても注目されています。
こうしたプロジェクトは、特にアフリカ、ラテンアメリカ、東南アジアといった気候変動の影響を受けやすい地域の農家にとって、重要な“共便益(co-benefits)”をもたらす可能性があります。
このような取り組みが広がっていくことで、段階的に中規模技術(mid-tech)を導入していき、供給チェーンのプロフェッショナル化や新たな収益機会の創出にもつながると期待されています。
ただし現在の市場動向を踏まえると、高品質なヘンプのハード(芯部)をバイオ炭として利用するよりも、建材用途として利用したほうが経済的に有利であるケースが多いのが現実です。バイオ炭向けが現実的になるのは、ハードの価格が大幅に下落した場合に限られるでしょう。
一方で、気候中立を目指す建材メーカーにとっては、「炭素除去型サプライチェーン」を構築すること自体が財務的に意味を持ちます。
たとえば、化石燃料への依存が残っている工場であっても、ヘンプのCO₂吸収分を自社の排出に対するオフセットとして利用することが可能ですが、販売できるのは“ネットネガティブ”(吸収>排出)であると認証された炭素証明書(クレジット)のみです。
そのため、ネットネガティブな生産を実現するには、「標準化されたライフサイクル評価(LCA)ガイドライン」に基づいて自社の工程を把握・改善することが必須となります。
誰が“クレジット”を得るのか?
ネットネガティブなサプライチェーンを構築するには、多くの関係者の連携が不可欠ですが、「その炭素利益を誰がどのように公平に受け取るべきか」という点は依然として明確ではありません。
たとえば、農家はCO₂吸収ポテンシャルのある原料(例:ヘンプ)を提供していますが、その“吸収能力”はこれまで市場価格にほとんど反映されてこなかったのが実情です。
一方で、製造業者がその原料を炭素貯留型製品(カーボンシンク)に加工すれば、環境価値は付加されますが、その分製品価格も上がり、競争力は低下するリスクも生まれます。
また、炭素クレジットの価値は「素材の使用フェーズ全体」に依存しており、消費者の役割も無視できません。たとえば、建材が後に解体・廃棄された場合、クレジットの価値は消失する恐れがあります。
現在、プロジェクトの開発、炭素貯留の管理、認証取得、維持コストを担っているのは製造業者であるため、金銭的リターン(クレジット収入)は基本的にメーカーに帰属しています。
しかしながら、高いネットネガティブ・バランスを持つ原料を農家に安定的に供給してもらうには、「農家にも正当な報酬が分配される構造」を作らなければなりません。そのためには、メーカーと農家がインセンティブを調整したサプライ契約を結び、長期的なパートナーシップを築くことが不可欠です。気候変動への本質的な対策として、サプライチェーン全体での協働が求められています。
編集部あとがき
今回の記事を以下、4つのポイントに整理しましたのでご参考ください。
1. EUの制度整備が「ヘンプ=カーボンネガティブ素材」としての認知を後押し
EUの「炭素除去およびカーボンファーミング規則(CRCF)」によって、バイオ炭や建材など長期的な炭素貯留手法が正式に制度化され、ヘンプが持つCO₂吸収能力や環境価値が経済的利益として評価される基盤が整いつつあります。
2. 高品質CDRクレジットの要件は極めて厳しく、スモールスケールでは困難
100年の炭素固定、不可逆性、LCA(ライフサイクル評価)、デジタル検証、ダブルカウント回避といった高度な基準を満たすことが求められ、これらは高度な専門性と資金力を要するため、小規模農家や中小企業の単独参入は困難。中~大規模な連携体制の構築が不可欠です。
3. バイオ炭 vs 建材:ヘンプ資材の最適用途は市場条件により異なる
現状では、高品質なヘンプハードをバイオ炭化するよりも建材用途で使用する方が収益性が高い。しかし、カーボンニュートラルを目指す建材メーカーにとっては、炭素除去サプライチェーンの構築が新たな収益・CSR戦略にもなるため、選択肢として現実味があります。
4. 「誰がクレジットを得るか?」の議論が不可欠。農家の正当な評価と報酬体系が求められる
CDRクレジットは現状、製造業者に集中していますが、CO₂吸収素材の供給元である農家にも正当なインセンティブを分配すべきという新たな倫理的・経済的議論が始まっている。今後は、メーカーと農家の「気候連携パートナーシップ」が、カーボン市場における次のスタンダードとなっていく可能性があります。